「Thank youじゃなくて、“ありがとうございます”って言うようになったんです。」
東京に移住して半年。シンガポールから来たある家庭の7歳の息子は、日本語の敬語と共に、**“相手を尊重する姿勢”**を身につけていた。
しかし、驚いたのはそれだけではありませんでした──「でも、ぼくはこう思うよ」と、自分の意見を丁寧に伝えるようになっていたのです。
日本での教育が、なぜ子どもたちに“礼儀”と“主体性”という一見相反する要素を育てるのか? その背景には、日本独自の教育文化と環境がありました。
■ 礼儀は「押しつけ」ではなく「空気づくり」
日本の教育現場では、「礼儀」を単なる“マナー”として教えることはしません。
代わりに、**「誰かが気持ちよく過ごすための“空気”を自分たちでつくる」**という価値観が徹底されています。
たとえば:
- 授業の開始と終了時の起立・礼
- 給食前後の「いただきます」「ごちそうさま」
- 廊下で人とすれ違うときの自然なお辞儀
- 忘れ物を拾って「はい、どうぞ」と渡すときの目線
これらはルールではなく、人との関係性を丁寧に築くための“生活の所作”。
移住してきた子どもたちは、クラスメートの姿を見ながら、自然とその“空気の美しさ”を学んでいきます。
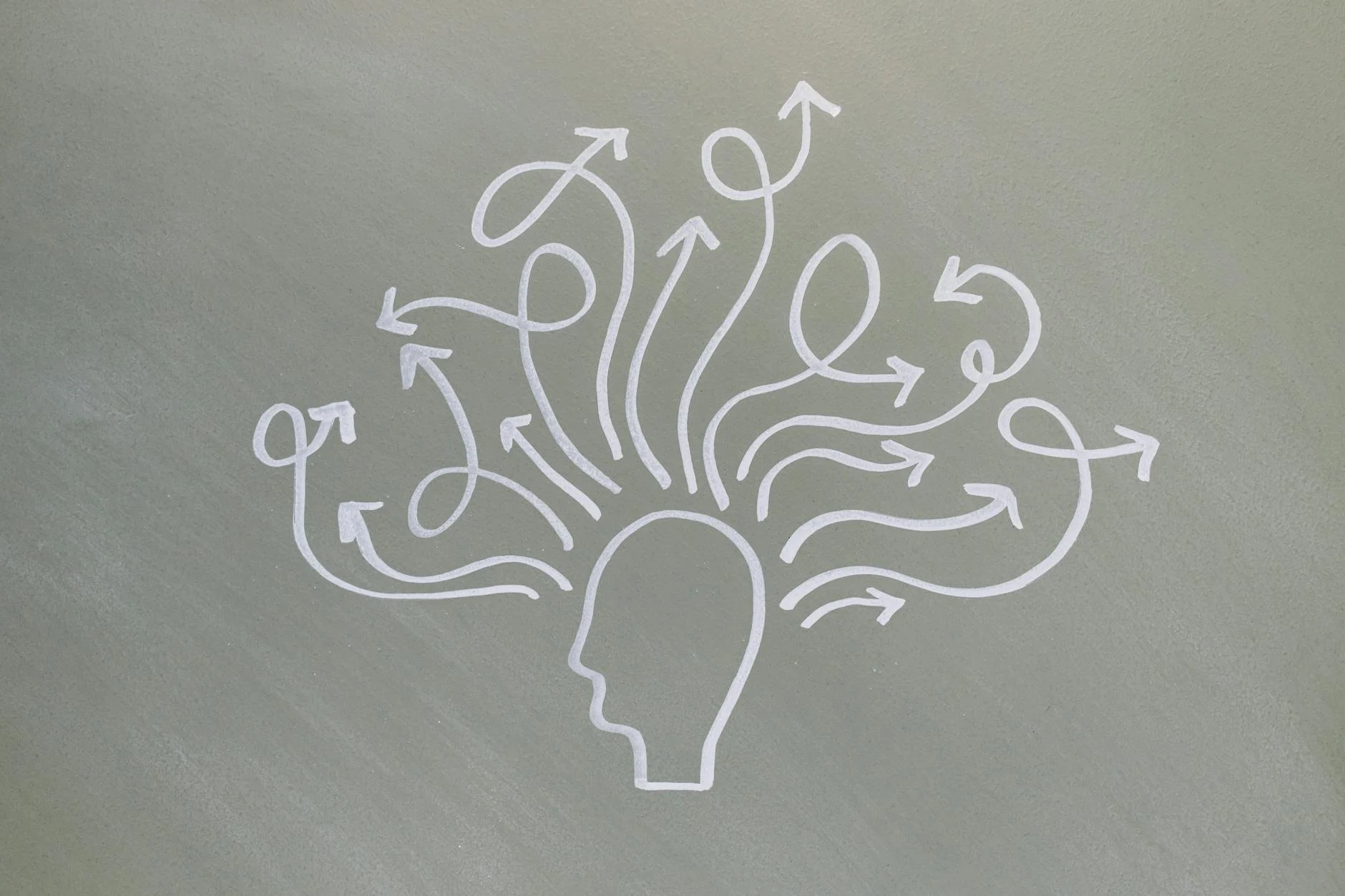
■ しかし、“自分の意見”も消されない
日本の教育が興味深いのは、「全体の調和」を重んじながらも、「自分の考えを持つこと」を否定しない点です。
- 意見発表の場では、「あなたはどう思う?」と先生が問いかける
- 図工の授業では「テーマ」だけ提示され、表現は自由
- 国語や社会では「登場人物の気持ち」や「自分ならどうするか」を話し合う
これにより、子どもたちは「場の空気を壊さずに、自分の軸を持つ」というスキルを身につけていきます。
まさに、国際社会で求められる“協調性と主体性のハイブリッド”です。
■ 実際の変化──ある家庭のケース
タイ出身の夫妻が、東京・文京区の小学校に通わせ始めた娘(8歳)のエピソード:
「入学当初、娘はとても内気で、授業中も発言できませんでした。でも3ヶ月後、家で“今日、私は違う意見だったけど、それを言っていいって先生が言ってくれた”と笑って話してくれたんです。」
また、息子(6歳)は毎朝、学校の門で先生に「おはようございます」とお辞儀することを日課にし、先生からの「ありがとう」の返事が嬉しくて仕方ない様子。
「誰かに丁寧に扱われた経験が、子どもの自己肯定感をこんなにも引き上げるのかと驚きました。」
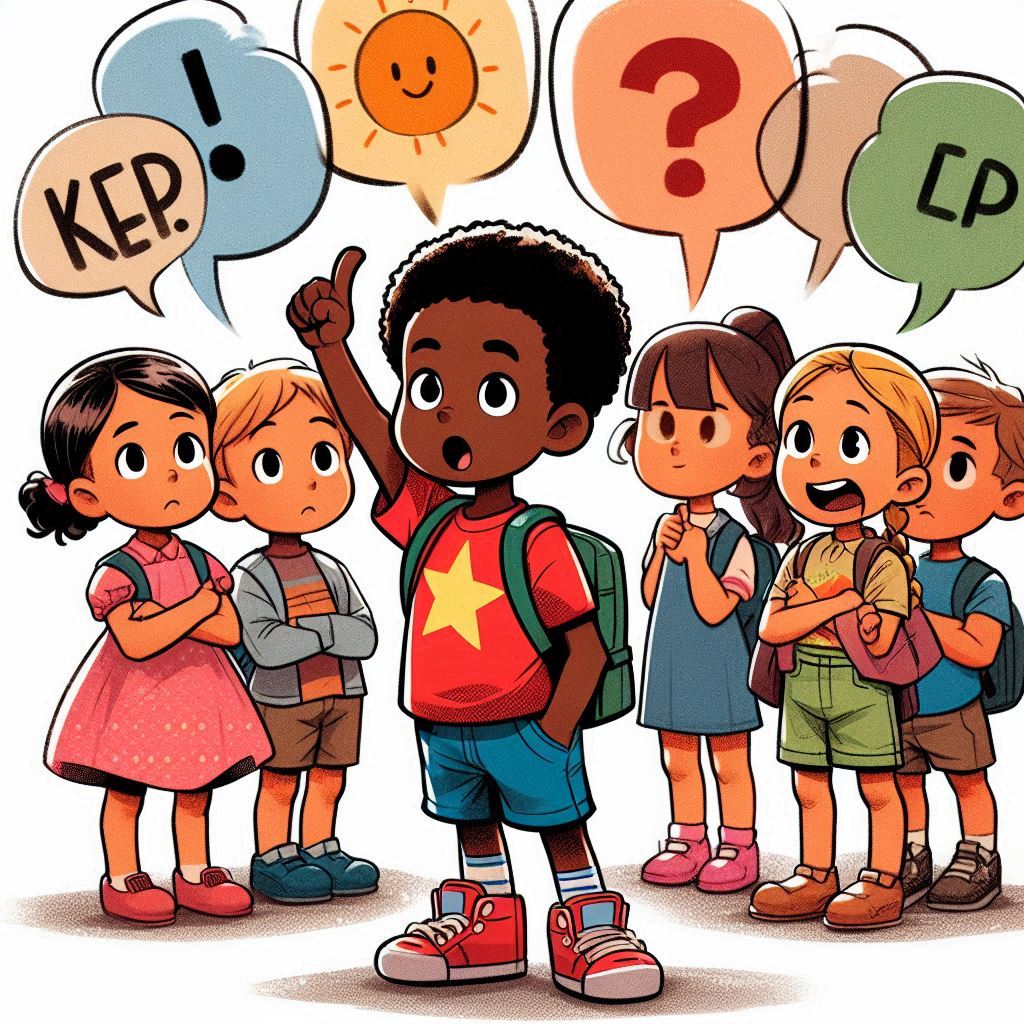
■ 海外の“個”と日本の“調和”を融合できる場所
欧米の教育は「個の尊重」を徹底し、自己主張を促します。
アジアの多くの国は「規律と結果」を重んじ、静かな競争を促します。
そんな中、日本の教育は珍しく、**「周囲を尊重しながら、自分の意見も持って良い」**というバランスを保っています。
これは、子どもにとって非常に高度な社会性の訓練でもあり、
- 国際社会で“空気を読める”けれど、
- 自分の価値も“しっかり語れる”
そんな**“育ちの良さ”と“主体性”が同居する人格形成**を促してくれるのです。
■ まとめ:“教え込む”のではなく“気づかせる”教育
子どもが「礼」を身につけるとき、それは「言葉」や「型」ではありません。
誰かを思いやる気持ちの延長線上に、自然と現れる行動です。
そして同時に、自分の意見を持ち、それを丁寧に表現する力は、「聞いてもらえる」という安心感から生まれます。
──そう、日本の教育とは、
“気づきと表現の反復”で子どもを育てていくアートなのです。




