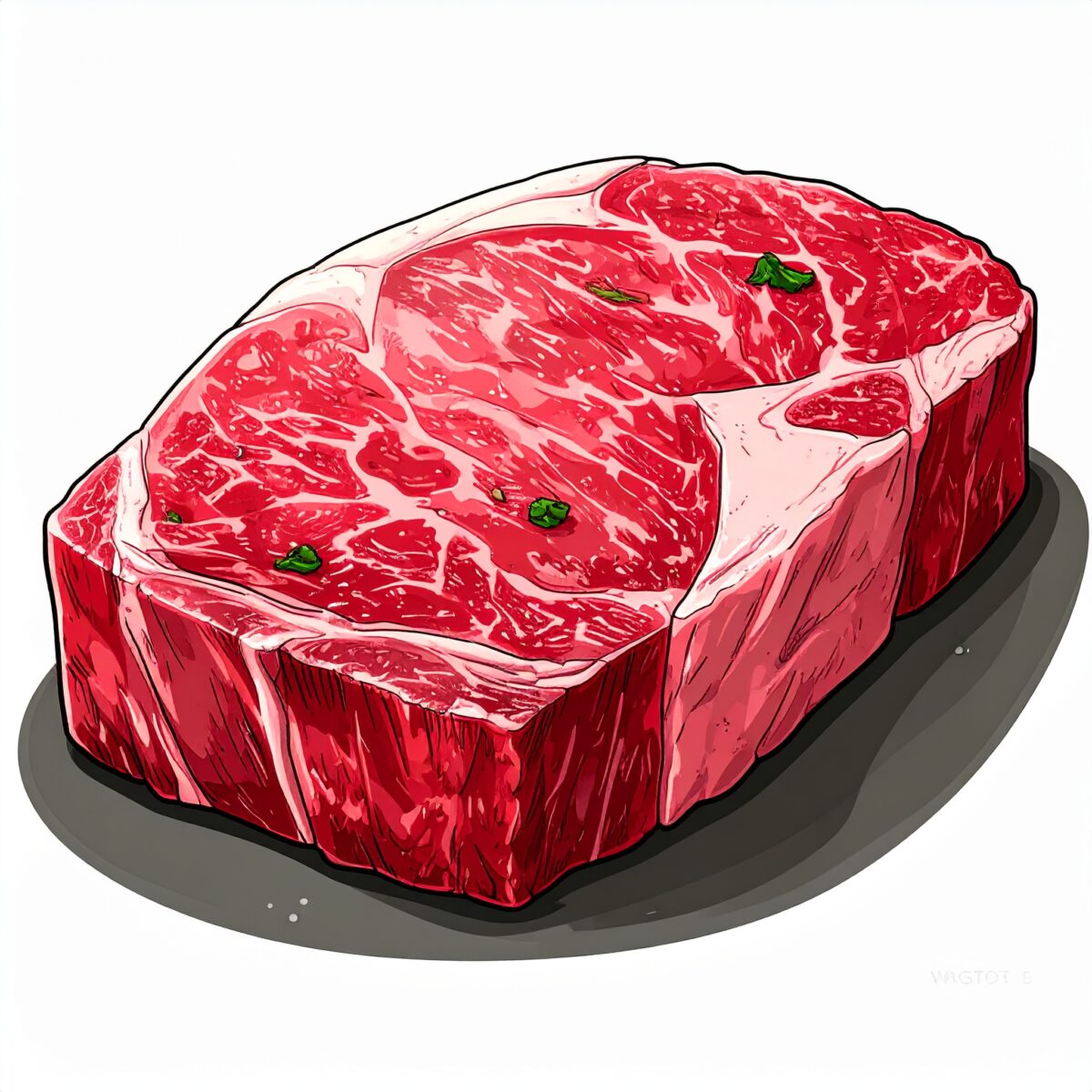かつて、和牛は「高級食材」の代名詞だった。霜降りの美しさ、舌の上でとろけるような脂、口に入れた瞬間の多幸感。それらは、祝いや贅沢の象徴として、特別な場面で選ばれる存在だった。しかし今、和牛をめぐる価値観は大きく変わりつつある。ただ美味しいだけではない、見た目や等級では測れない「哲学としての和牛」が、静かに浸透し始めている。
和牛とは、もともと日本の在来種を基に改良された肉用牛であり、その品質管理は極めて厳格である。肉質や脂肪交雑(いわゆる霜降り)、歩留まりなどによって等級が決められ、市場ではその評価に応じた価格がつけられる。これまでの和牛ブランドは、こうした等級や見た目を重視し、より霜降りが強く、より柔らかい肉を目指して生産されてきた。
だが、その一方で、「本当に求められている味とは何か」「牛にとっての幸せとは何か」「持続可能な畜産とは何か」といった問いを突き詰める生産者たちが現れている。彼らは、和牛を「育てることそのものが哲学である」と考え、個体ごとの性格や成長のリズム、ストレスの有無までも含めて飼育方法を見直している。

次世代の和牛ブランドは、まず「飼料」に明確なこだわりを持つ。輸入穀物だけに頼らず、地元の稲わらや麦、発酵飼料を取り入れることで、牛の消化に負担をかけず、肉質に自然な旨味を持たせる。また、抗生物質や成長促進剤の使用を最小限に抑えることで、安全性を高めると同時に、牛の健康寿命を延ばす試みもなされている。
環境ストレスの軽減も重要なテーマだ。牛舎の広さや清潔さ、風通し、照明、音環境など、飼育空間の整備は肉質にも直結する。自由に動き回れるスペースを与え、牛同士のストレスが少ない群管理を採用する牧場では、脂の質が軽く、赤身の味わいが濃い肉に育ちやすい傾向がある。こうした自然に近い飼育環境の中で育った牛は、まさに「風土の味」を体現する存在となる。
また、近年注目されているのが、「赤身肉」への再評価である。霜降り至上主義から離れ、牛本来の筋肉の香りや歯ごたえ、余韻を楽しむという価値観が、料理人や消費者の間で広がっている。脂の美しさではなく、「噛みしめて美味しい和牛」へ。これは、肉に対する認識の変化であると同時に、生産現場における「何を育てるか」という目的の転換でもある。
さらには、和牛の「顔が見える」時代が来ている。個体識別番号によってトレーサビリティが保証されるだけでなく、生産者の名前や飼育日記が公開される取り組みも増えている。牛の名前、育った場所、食べてきたもの、どのような思いで育てられたか。消費者がそれらを知ったうえで選ぶという行為は、単なる買い物ではなく、価値観の共有と言えるだろう。

こうした動きの背景には、食と倫理の問題もある。畜産は大量の資源を必要とし、環境負荷が高いとされる一方で、命を扱う産業であるという重みもある。その中で、牛の命を余すことなく使い、部位によっては加工品や出汁、革製品としても活用する「全頭利用」や、地域の資源を循環させる「地産地消型畜産」が注目されている。和牛は、ただ高価で美味しいだけでなく、持続可能な社会のあり方を問い直す存在になりつつある。
飲食の現場においても、次世代の和牛は新しい可能性を拓いている。ミシュラン店や海外のレストランでは、和牛を単なる高級素材としてではなく、ストーリーを持つ食材として捉える流れが強まっている。特定の牧場から届いた一頭分の牛を、余すことなく使い切るメニュー構成や、赤身肉を中心に据えたコース展開など、和牛の“新しい顔”が現れている。
そして、なによりも興味深いのは、このような価値転換が、消費者からの問いかけによって後押しされているという事実である。「どこで育ったのか」「何を食べてきたのか」「誰が育てたのか」──そうした素朴な疑問に対して、丁寧に答えようとする生産者と、それを受け止めようとする食べ手。その関係性が、これからの和牛ブランドを形づくっていく。
和牛は、もはや「希少で高価な肉」ではない。その裏にある命と時間、土地と人のつながりが、肉の味わいに深みを与え、語る力を宿すようになった。そしてそれは、ステータスのための消費から、価値を共有する「選択」へと進化している。
ステータスから哲学へ。和牛の未来は、食べるという行為を通じて、いかに世界とつながるかを私たちに問いかけている。