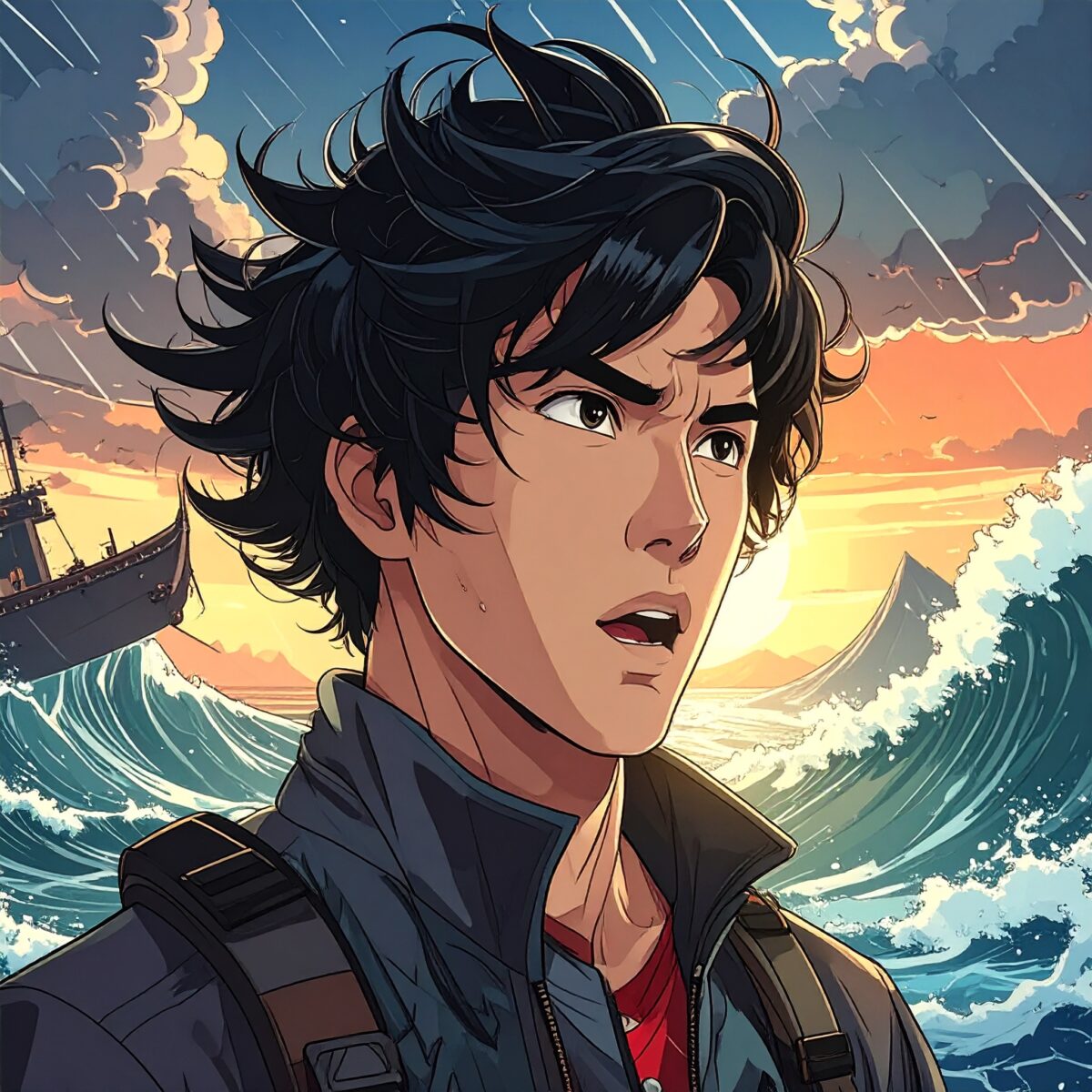日本で暮らしていると避けられないのが台風・地震・大雨・洪水などの自然災害。
賃貸物件に住んでいる場合、自分が所有者ではないからこそ、「被害を受けたときはどうすればいいのか?」「誰が直してくれるのか?」「保険に入っていない場合はどうなるのか?」といった不安を抱えることもある。
実は、こうした災害時には火災保険以外にも利用できる支援制度や相談先が複数存在する。
この記事では、自然災害で被害を受けた際に活用できる“保険以外”の対応ルートと、被害後にすぐ取るべき行動について解説する。
まず最初にするべきこと:状況を正確に記録する
被害を受けた場合、まず行うべきは**「被害の証拠を残す」こと**。
✅ 写真・動画を撮影
-
破損した壁、壊れた家具、浸水した床などを日付がわかる形で複数アングルで記録
-
損傷した設備が貸主所有か借主所有か区別する(エアコン、給湯器、建具など)
✅ 管理会社または貸主に連絡
-
修繕の対象・順序・応急対応の範囲について明確にしておく
-
借主が勝手に業者を呼ぶと費用を自己負担する可能性がある

保険に入っていない、または適用外のときに使える支援制度
火災保険の加入がない、または補償の範囲外(地震被害など)の場合でも、行政や自治体の支援制度が存在する。
1. 自治体の「被災者生活再建支援制度」
-
自然災害で住まいに甚大な被害を受けた場合、最大300万円まで支援金が支給される制度
-
原則として世帯単位での申請となる(世帯主が申請)
-
半壊や全壊、長期避難など被害の程度に応じて支給額が変わる
-
罹災証明書の取得が必須
※対象外の災害もあるため、市区町村の窓口で必ず確認すること
2. 罹災証明書の取得
災害による損害を証明するための公的書類。
主に市区町村の役所・役場で発行される。
用途:
-
自治体の支援金申請
-
各種公共料金の減免
-
契約解除時の違約金免除交渉
-
被災者向け一時住宅入居申請
取得の流れ:
-
被害発生後、役所に申請(電話 or Web)
-
職員による現地調査または写真提出
-
数日後に証明書が発行される
3. 公共料金の減免・猶予申請
災害発生時は、電気・ガス・水道・通信料金などに対して、支払い猶予や一部減免が適用されることがある。
主な対応例:
-
請求期限の延長
-
一時的な支払い免除
-
違約金・再開通手数料の免除
→ 各サービス会社の「災害時の特別対応窓口」に直接連絡して申請する。
4. 雇用や生活資金の相談(生活福祉資金貸付制度)
災害で収入が減少した、職を失った、生活が困難になった場合は、都道府県の社会福祉協議会による無利子・低利子貸付制度を利用できる。
-
緊急小口資金(10万円程度)
-
総合支援資金(月20万円程度)など
→ 最寄りの社会福祉協議会に問い合わせ、申請書を取得する。
建物や設備が破損した場合の対応は?
| 所有者 | 責任と対応内容 |
|---|---|
| 建物本体・壁・窓・屋根 | 原則として貸主の責任で修繕 |
| 設備(エアコン、給湯器、ドアなど) | 契約書で「貸主設置の設備」であれば修繕義務は貸主側 |
| 借主の家具・家電・私物 | 借主の所有物なので、火災保険や家財保険の対象か確認 |
| 建物の使用が難しくなった | 管理会社と協議し、「一時退去」「契約解除」などを判断 |

契約を継続できないレベルの損害が出たときは?
災害で「部屋に住み続けることが不可能」と判断された場合は、賃貸借契約の解除や家賃免除が認められることもある。
条件と判断基準の一例:
-
天災によって居住不能となった場合(民法第611条)
-
建物の全壊・半壊など罹災証明の発行内容に基づく
-
貸主が修繕に応じない、または時間を要する場合
-
契約書の「不可抗力による免責条項」が適用される場合
トラブルを避けるためにやるべきこと
-
すぐに連絡・報告・記録を行う(写真・動画が重要)
-
管理会社やオーナーと必ず協議する(自己判断は避ける)
-
自治体や専門窓口に遠慮なく相談する(支援制度は「申請主義」)
-
契約書の特約・保険の補償範囲を確認しておく(災害条項の有無)
自然災害は予測できないものだが、被害を最小限に抑えるための制度や支援は確実に存在する。
火災保険に頼るだけでなく、公的な支援や正しい情報にアクセスできることが、住まいと暮らしを守る力になる。