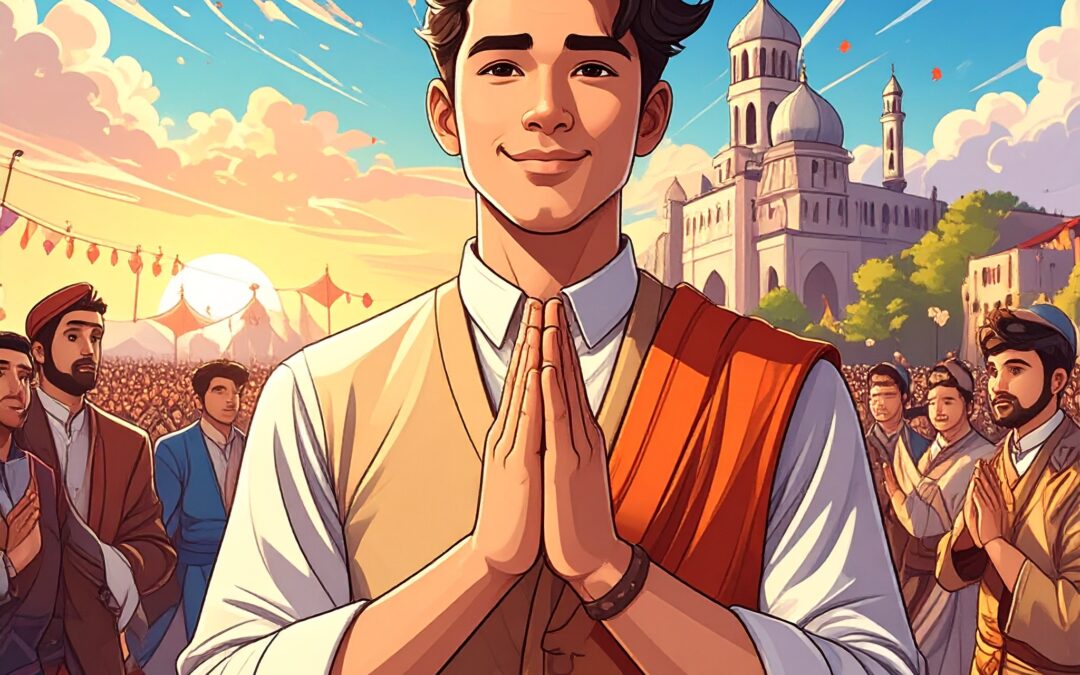by info@pacific-realty.jp | Jul 3, 2025 | NEWS
日本のビジネスシーンにおいて、名刺交換は単なる自己紹介ではない。それは互いを尊重し、関係の始まりに敬意を示すための静かな儀式である。渡すタイミング、受け取る姿勢、添える言葉。その一つ一つに気配りがあり、日本人ならではの人間関係に対する価値観があらわれている。 名刺は、その人の肩書や所属を表す紙の一枚にすぎない。だが、日本ではそれを丁寧に両手で差し出し、胸の高さかそれよりやや低い位置で相手の目を見ながら挨拶を交わす。その所作は一種の儀礼ともいえるものであり、最初の出会いの瞬間から相手を軽んじないという姿勢を伝えている。...

by info@pacific-realty.jp | Jul 3, 2025 | NEWS
都市に暮らす人々は、常に音に囲まれている。駅のアナウンス、車のエンジン音、スマートフォンの通知、交差点の雑踏。それらはすべて生活の一部として自然に受け入れられているが、意識を向ければ向けるほど、静けさがどれほど貴重なものかに気づく。 かつては当たり前だった静寂が、今では手に入りにくい贅沢になりつつある。忙しさに追われ、次から次へと情報が押し寄せる中で、音がない時間を求める人が増えている。静けさの中に身を置くことで、自分自身と向き合い、心を整える時間が得られるからである。...

by info@pacific-realty.jp | Jul 3, 2025 | NEWS
部屋を片づけると、なぜか心が軽くなることがある。空間が整うことで気分まで整うという感覚は、多くの人が無意識に感じていることだろう。日本では古くから、掃除や整理整頓は単なる家事ではなく、心の状態を映すものとして大切にされてきた。 寺院では、掃除が修行の一環として行われてきた。朝の時間に庭を掃き、廊下を拭き、仏具を整える。そこにあるのは単に清潔を保つという目的だけではない。ほこりや汚れを丁寧に拭い取る行為を通して、煩悩や余分な感情を取り除き、無駄のない静かな心に近づこうとする意識がある。...
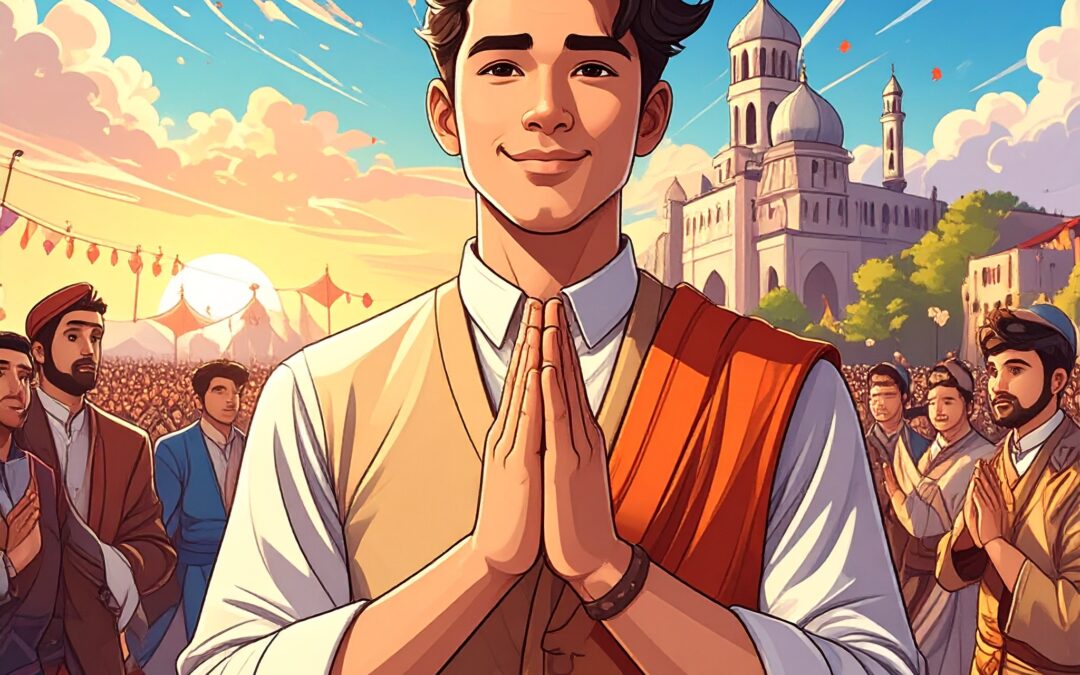
by info@pacific-realty.jp | Jul 3, 2025 | NEWS
日本各地で行われる祭りは、単なる観光行事や娯楽ではない.その根底には人々の祈りと願いがあり、自然や神とつながる営みとして続けられてきた.華やかな衣装や山車の動きに目を奪われがちだが、そこには共同体が受け継いできた精神性が脈々と息づいている. かつての日本の暮らしは、自然の影響を強く受けていた.台風や干ばつは作物の出来を左右し、日々の暮らしの安定を揺るがすものだった.そうしたなかで人々は、目に見えない力に祈りを捧げ、祭りというかたちで感謝や願いを表現してきた.五穀豊穣や無病息災、子どもの成長を願う祭りは今も各地に残されている....

by info@pacific-realty.jp | Jul 3, 2025 | NEWS
「和を以て貴しとなす」。この言葉に象徴されるように、日本では古くから「和(わ)」が最も重んじられる価値観として根付いている。個の主張を押し通すよりも、他者との調和を図ること。勝ち負けよりも、対立を避けて共に在ること。そうした思考は、社会の構造、日常の所作、人と人との距離感にまで深く影響を与えている。...