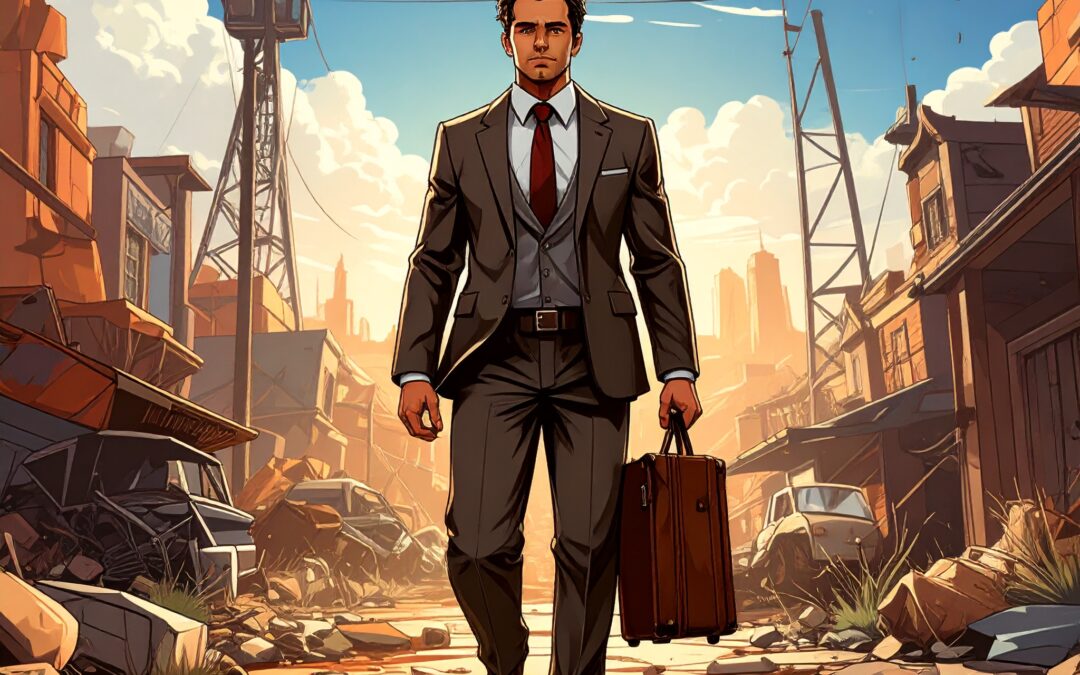by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
2001年に公開されたスタジオジブリ作品『千と千尋の神隠し』は、日本国内で驚異的な大ヒットを記録しただけでなく、世界各国で深い共感と称賛を受け、2003年にはアカデミー賞長編アニメーション賞を受賞した。だが、この作品が本当に描いていたのは、目に見えるファンタジーではない。外国人たちをも魅了したのは、実は“日本人の心の奥底に眠る感性”──つまり「日本の魂」だったのではないか。 懐かしくて新しい、“異界”の構造...

by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
旅の記憶に残るのは、必ずしも見た景色だけではない。ふと耳にしたメロディ、土地のことばで紡がれる歌声──そんな“音の体験”こそが、心に残る文化との出会いになる。 近年、日本の「昔の歌」──わらべ歌、民謡、童謡、昭和歌謡などを観光資源として活用する“音の文化ツーリズム”が、国内外で注目を集めている。音楽を「聞く」から「体験する」へと変化させることで、より深く日本文化に触れられる新しい旅の形が生まれているのだ。 観光客の耳をとらえる“うたの時間”...
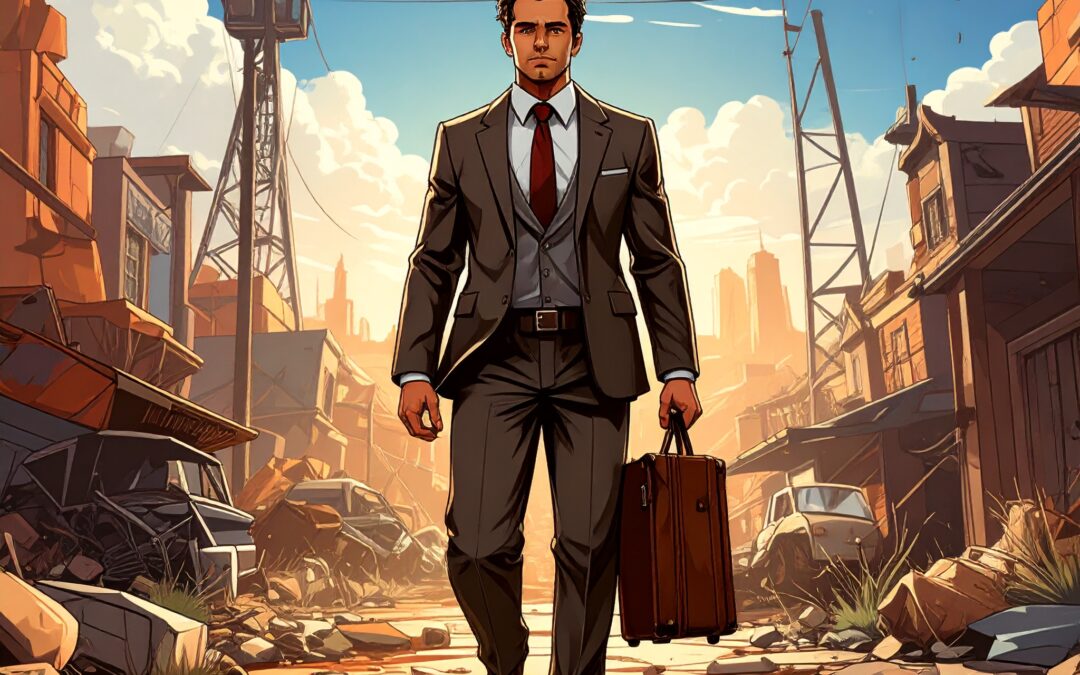
by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
「歌は生きものだ。歌い継がれなければ、風化してしまう」そう語るのは、ニューヨークを拠点に活動する邦楽シンガー・真理子氏。彼女は近年、日本のわらべ歌や民謡、昭和初期の叙情歌など、“口伝えで残されてきたうた”を海外で収集・翻唱し、記録・発信するプロジェクトを進めている。 高度にデジタル化された現代にあって、アナログな“うたの記憶”が失われようとしている今、日本出身のアーティストたちが「うたを遺す」ために立ち上がっている。 消えゆく「記憶のうた」...

by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
小気味よいリズムにのせて、日常や世情を言葉で刻む──そんなスタイルは、ヒップホップだけのものではない。江戸時代の庶民が口ずさんでいた「端唄(はうた)」や「都々逸(どどいつ)」にも、実は現代ラップと通じる“語りの文化”が息づいていた。 いま、日本の伝統音楽とヒップホップが交差する新たな潮流が生まれつつある。江戸の言葉遊びと現代のビートが出会うとき、そこには時代を超えた“ことばの自由”が響き出す。 江戸の「言葉あそび」はリズムの芸...

by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
「ふるさと」「赤とんぼ」「さくらさくら」──どこか懐かしい旋律に、日本語のやさしい響きが重なる。これらの日本の“昔の歌”が、いまアジア各地の学校で日本語教育の教材として活用されはじめている。 文字や文法だけでは伝えきれない「日本語のリズム」や「文化の背景」が、歌を通して自然に伝わる。そんな“音を介した言語学習”が、日本語学習者たちに新たな気づきと関心をもたらしているのだ。 言葉と音楽が出会うとき、学びは深まる...

by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
カチリと針を落とす音、回転する黒い円盤、そしてスピーカーから流れ出すやわらかなノイズ混じりの音楽──いま、アナログレコードを通して「昭和の日本」を体感しようとする海外バイヤーが急増している。 シティポップ、歌謡曲、ジャズ、民謡、さらには映画音楽やCMソングまで──昭和期のレコードが、ヴィンテージではなく“今だからこそ欲しい音”として、世界のカルチャーシーンで脚光を浴びているのだ。 デジタル時代に“モノとしての音”を求める...