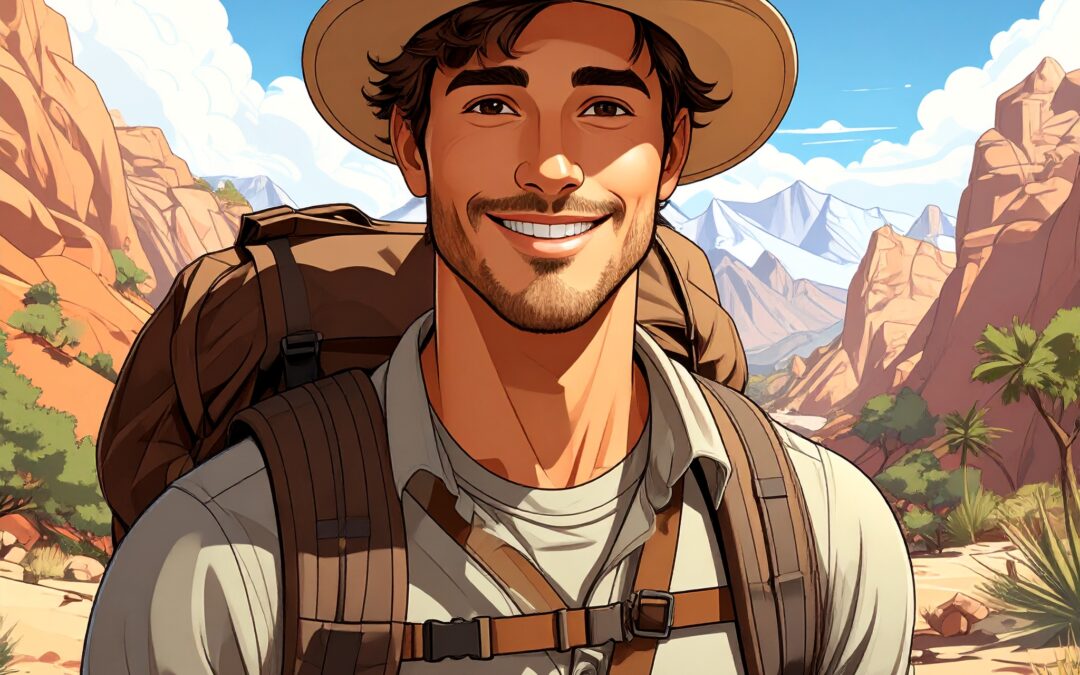by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
江戸時代、町の暮らしを支えていた「井戸」。その周囲には、自然と人が集まり、家事の合間に情報交換や雑談が生まれていた。この「井戸端会議」と呼ばれる光景が、いまSNS時代の人間関係に疲れた現代人にとって、“新しい理想のコミュニケーション”として再評価されている。 画面越しの会議、時間を区切られたチャット、疲れるメッセージのやり取り──そんな「繋がりすぎる社会」の中で、井戸端の“ゆるやかなつながり”が、むしろ新鮮に映るのだ。 情報よりも“空気”を共有する場所...
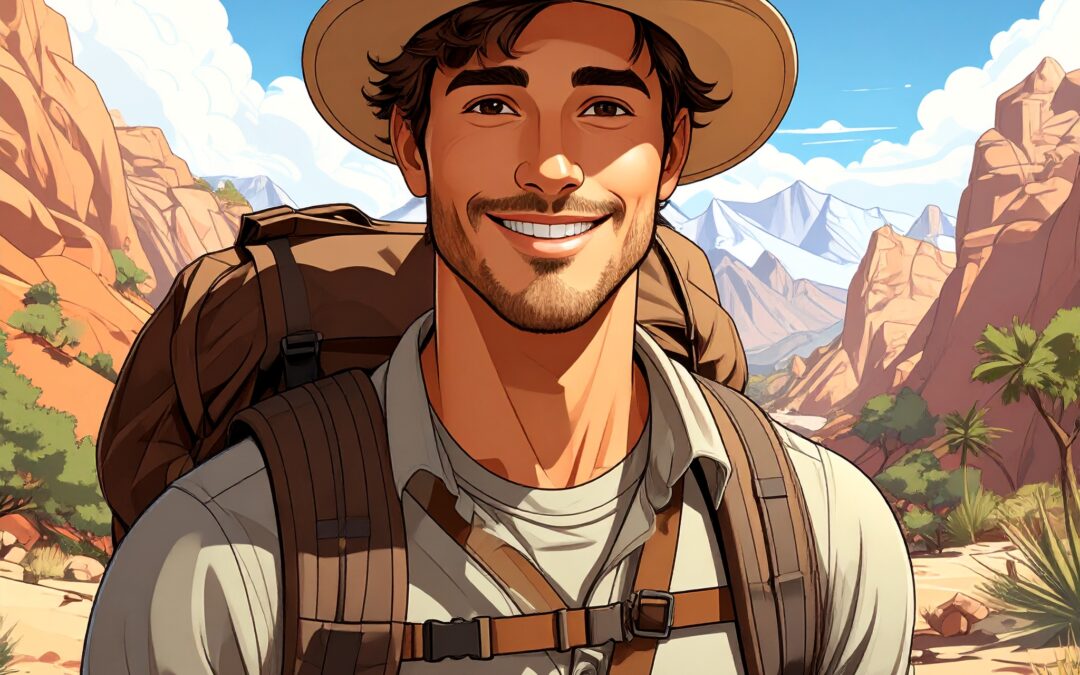
by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
にぎやかな観光地から少し離れた静かな小道。のれんをくぐると、そこには低い天井と畳の間、湯気の立つ湯呑み、そしてゆっくりと時が流れる空間が広がっている──江戸時代の「茶屋」を再現した体験型の店が、いま海外旅行者の間で人気を集めている。 現代の都市生活に慣れた人々にとって、江戸の茶屋はただお茶を飲む場所ではない。「何もしない時間を楽しむ」ための、特別な場となっているのだ。 茶屋とは、日常の中の“ととのえ空間”...

by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
クラクション、スマホ通知、機械音──現代都市に暮らす私たちは、気づかぬうちに「音の洪水」の中で日々を過ごしている。だが、そんな“騒がしさ”に疲れた世界がいま注目しているのが、江戸時代の日本にあった“静けさの文化”だ。 江戸の暮らしは、今からは想像できないほど静かだった。家にはテレビも冷蔵庫もなく、道路には車もバイクもない。日が暮れれば照明も行灯のやさしい灯りだけ。そんな「ノイズレスな環境」がもたらす心地よさが、現代人の感性を癒し始めている。 音を“消す”のではなく、“整える”文化...

by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
現代の暮らしには、スイッチ一つで温まり、照らし、飲める便利な道具が揃っている。だがいま、その利便性の対極にあるような“昔の生活道具”──火鉢、行灯、井戸といった江戸時代のアイテムが、ヨーロッパやアジアのデザイナーや生活文化愛好家たちの心をとらえている。 決してハイテクではない。むしろ“手間がかかる”“不便”な道具たち。それでも「だからこそ美しい」「だからこそ心が動く」と、静かに注目を集めているのだ。 火鉢──“火”を囲む、暮らしの中心...

by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
江戸時代の日本人は、いまのように冷蔵庫もコンビニもない暮らしの中で、旬の食材を活かし、無駄なく丁寧に料理をしていた。その素朴で工夫に満ちた“江戸ごはん”が、いまフランスや北欧などの海外シェフの間で「持続可能な食文化」として注目を集めている。 肉中心ではなく、野菜・豆・魚を主役とする食事。発酵や乾物を活用し、食材の端から端までを使い切る知恵。それは、フードロス削減やローカル志向が進む世界の食の潮流とも自然に重なっている。 「一汁一菜」に学ぶ、最小で最大の満足...

by info@pacific-realty.jp | Jun 27, 2025 | NEWS
「江戸時代」と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは、刀を携えた侍の姿や将軍のいる城下町の風景だろう。だが今、海外で静かに注目されているのは、そうした“武士の物語”ではなく、庶民たちが紡いできた「暮らしの知恵」だ。 節約、再利用、共助、自然との共生──そうした生活の工夫が、現代の都市生活における“サステナブルなヒント”として再評価されている。 江戸の庶民が大切にした「もったいない精神」...