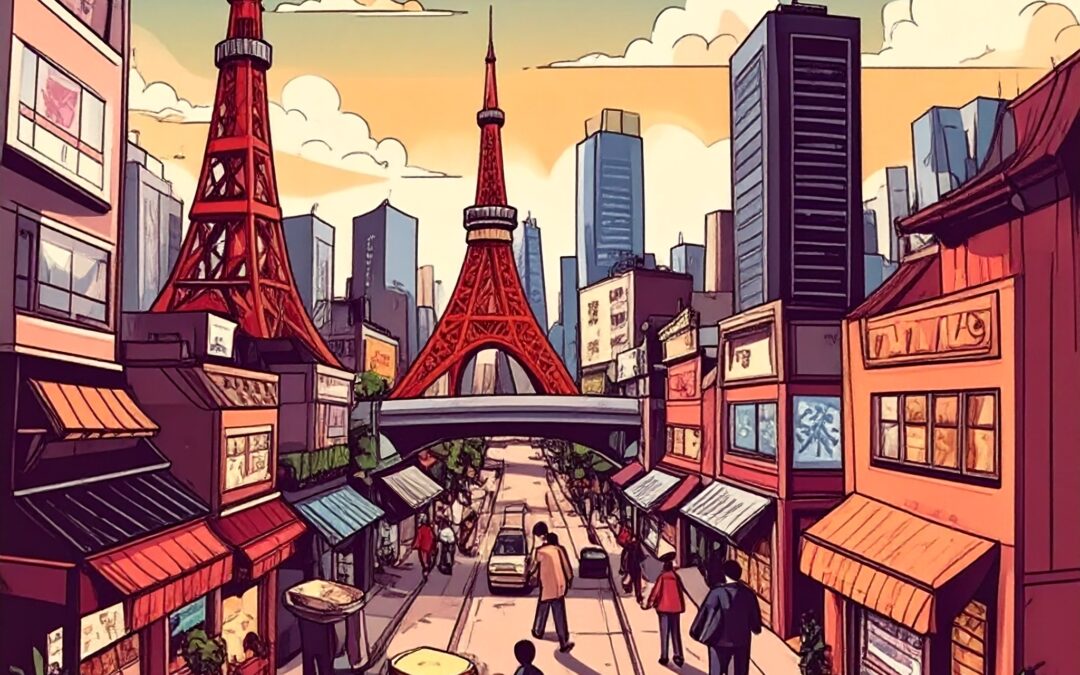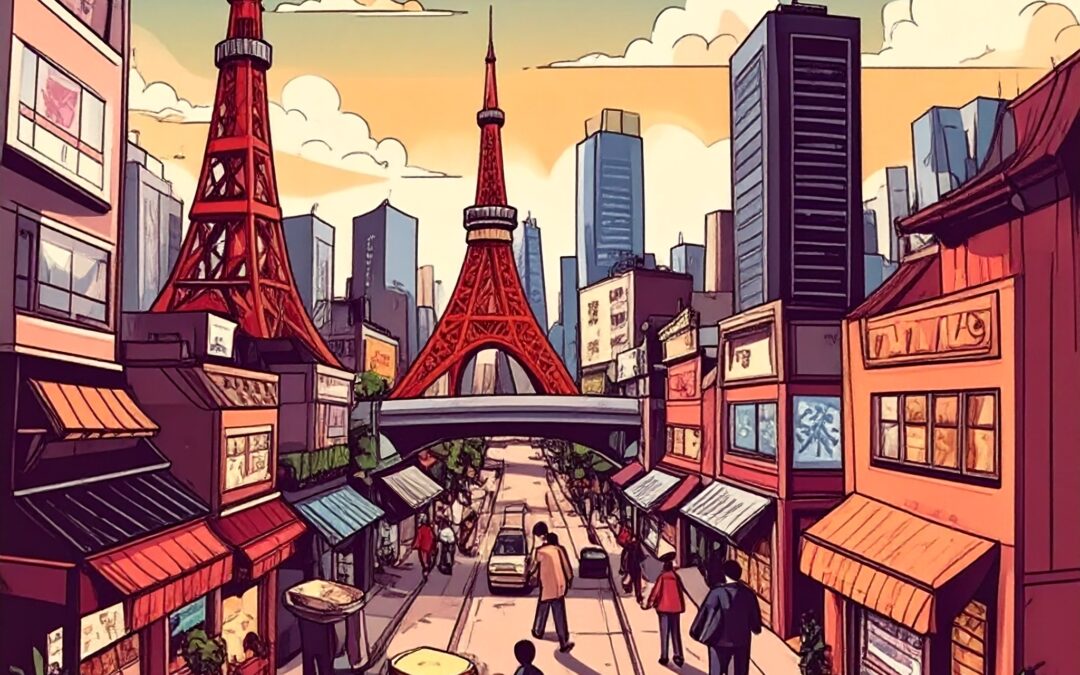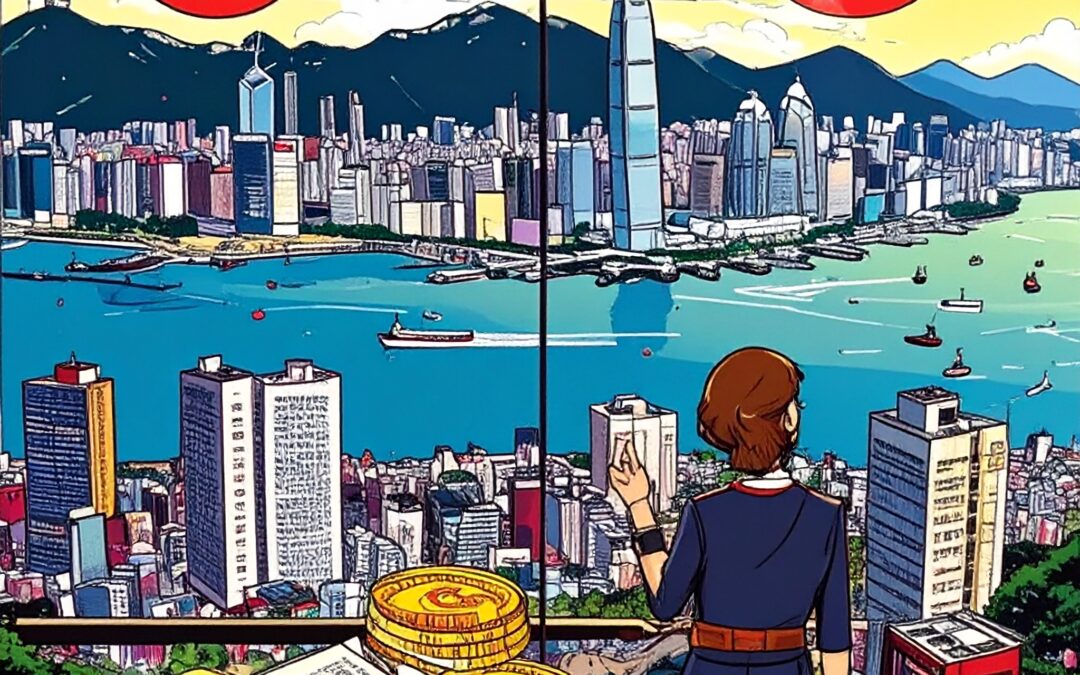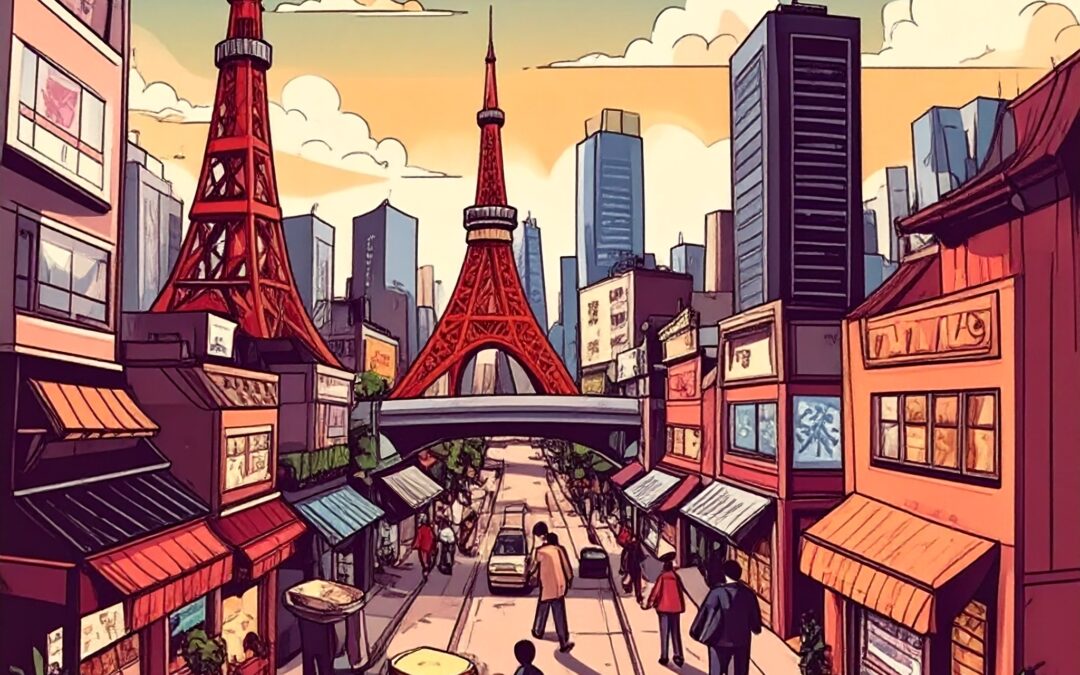
by info@pacific-realty.jp | Jun 5, 2025 | NEWS
「日本の都市は、どこも割安に見える。でも、本当に“お得な投資先”はどこですか?」 いま、円安の恩恵を最大限に活かせるのが「日本不動産への外貨投資」です。 中でも注目されているのが、日本三大都市──東京・大阪・福岡。 それぞれに個性と魅力がありながら、「割安で買えるタイミング」は限られています。 本記事では、富裕層・投資家目線で「いま最もコスパの高い都市はどこか?」を比較しながら検証します。 ■ まず確認:円安のインパクトとは? 2025年現在、1ドル=150円前後という水準は、ここ数十年で見ても極端な円安水準。...

by info@pacific-realty.jp | Jun 5, 2025 | NEWS
「どう考えても、この品質でこの価格は“おかしいほど安い”。」 これは、ロンドンに拠点を持つ不動産ファンド代表が、東京・港区の築浅マンションを見学した際のコメントです。 物件そのものの質、管理体制、周辺環境、安全性──すべてが高水準にもかかわらず、“価格だけが取り残されている”。 そう、世界から見た日本の不動産は、今や「過小評価された優良資産」。 この記事では、なぜ日本の不動産が“割安”と見なされ、海外富裕層の注目を集めているのか、その背景を解説します。 ■ 「割安」とは、ただの“価格の安さ”ではない...
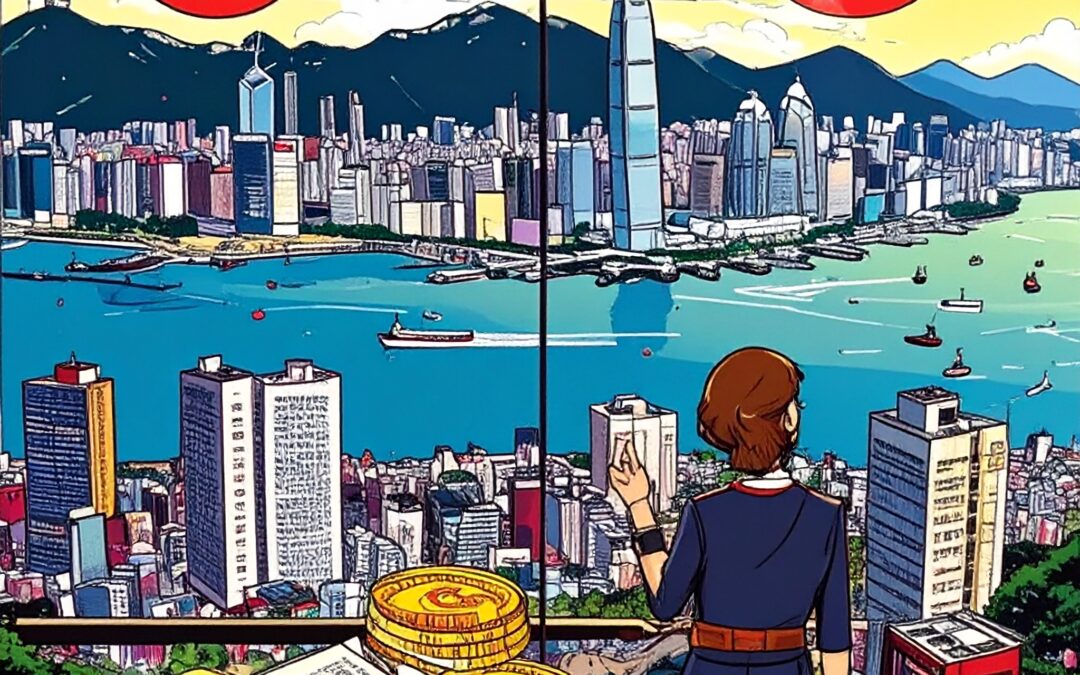
by info@pacific-realty.jp | Jun 5, 2025 | NEWS
「教育の質は変わらない。でも、出ていくお金がまったく違う。」 これは香港の経営者が、東京のインターナショナルスクールを視察した後の率直な感想です。 今、教育移住を検討するアジアの富裕層の間で、“東京”が再評価されています。 その理由のひとつが、国際的なカリキュラムに対応した学校が多く、かつ学費が“割安”に感じられることです。 本記事では、香港と東京を中心に「インターナショナルスクールの教育コストと内容」を比較し、なぜ東京が“教育面でも投資妙味のある都市”なのかを解説します。 ■ 学費比較:同じカリキュラムでも、ここまで差がある...

by info@pacific-realty.jp | Jun 5, 2025 | NEWS
「東京のレストランは、値段を見ずに頼んでもびっくりしない。」 そう語るのは、シンガポールに本拠を構える投資家。彼は仕事の関係で毎月のように東京を訪れ、そのたびに“食費感覚”の違いに驚かされると言います。 東南アジアや欧米の大都市と比べても、日本、とくに東京の**“外食コストの低さ”と“満足度の高さ”**は群を抜いています。 今回は、シンガポールと東京の外食コストを比較しながら、日本がいかに“高品質で割安な食文化を持つ国”であるかを掘り下げていきます。 ■ 価格で比較:同じ内容でも、ここまで違う 食事内容 シンガポールの価格(1人)...

by info@pacific-realty.jp | Jun 5, 2025 | NEWS
「月100万円なんて、ロンドンじゃ家賃だけで消える。」 そう嘆いたのは、ロンドンで暮らす香港出身のファミリー。 世界の富裕層にとって“月100万円”は、決して特別な金額ではありません。 しかし──**日本にそのまま移住したとき、その100万円が“どれだけ贅沢になるか”**をご存知でしょうか? 今回は、世界主要都市と比較しながら、東京・大阪・福岡での「月100万円のリアルな生活像」を解説します。 ■ まず、100万円=約6,500USD でできること(各都市比較) 都市 月100万円でできる暮らし(夫婦+子1人想定) 東京 港区...

by info@pacific-realty.jp | Jun 5, 2025 | NEWS
「昔はロンドンやシンガポールが主流だった。でも今は、“東京が一番安心できる”と感じている。」 これは、香港で複数の企業を経営する40代の実業家が語った言葉。 近年、タイ・香港・シンガポールといったアジアの富裕層の間で“東京移住”が現実的な選択肢として急浮上しています。 いま、なぜ彼らが東京を選ぶのか? その背景には、安全・教育・生活コスト・投資環境など、あらゆる視点での“バランスの良さ”がありました。 ■ かつての定番は“シンガポール”や“欧米” 富裕層の移住先として長らく人気だったのは:...